妊娠中にする「おりもの検査」ってどんな意味があるの?クラミジア、BV、GBSの基本的なことを調べてみた。
- 2020.04.03
- 妊娠中の悩み

こんにちは。さきちです。
2回目の妊娠生活も”残りわずか”となってまいりました。
母子手帳を見ると、これまでした「検査の結果」がいろいろ記されています。
大きく分けて
●血液検査
●微生物検査
●がん検診(子宮がん)
この3つに分けられます。
血液検査とがん検診については、比較的項目が理解しやすいです。
でも「微生物検査って…なんだろう…?」
私が検査したのは
●クラミジア
●BV
●GBS(B群連鎖球菌)
の3つのようです。
今回はこの3つの検査について、どんな意味があるのか調べてみました。
クラミジア
クラミジアは最も多い性感染症で、女性の感染者の5人に4人までが自覚症状がなく、放置すると卵管炎など不妊症の原因になるそうです。
クラミジア感染症にはいくつかの種類がありますが、感染者の激増しているのは「クラミジア・トラコマティス」というタイプで、多くは、性行為により性器粘膜で感染を起こします。
妊婦健診で、クラミジアの検査が行われるのは、クラミジアに感染していると、赤ちゃんに影響を与えるリスクがあるからです。
妊娠中の影響について
妊娠初期~中期
☑妊娠初期~中期の妊婦さんがクラミジアに感染していると、「絨毛膜羊膜炎(じゅうもうまくようまくえん)」という病気を発症して、早産や流産を招く恐れがあります。
*絨毛膜羊膜炎:早産や破水の最大の原因になるもの。
お腹の中で赤ちゃんは、「脱落膜」「絨毛膜」「羊膜」という3層の膜で包まれています。 そのうちの、「絨毛膜」と「羊膜」に炎症が起こる病気を、絨毛膜羊膜炎と言います。
絨毛膜羊膜炎になると、絨毛膜と羊膜が炎症の影響で薄くなって破れてしまうことがあります。
また、同時に「プロスタグランジン」という子宮収縮を促すホルモンが多く分泌されるようになり、予定より早い時期に子宮収縮が始まり、 早期破水や切迫早産、流産、常位胎盤早期剥離(胎児が子宮内にいるうちに、胎盤が子宮から剥がれる非常に危険な状態)の原因になることがあります。
妊娠後期
☑出産が近づく妊娠後期になると、産道感染のリスクが出てきます。
産道感染とは、出産時に赤ちゃんが産道を通過する際に、病原菌に感染してしまうことです。
妊娠中にクラミジアに感染して無治療のまま出産をすると、 産道感染によって18~50%が「新生児結膜炎」を、3~18%が「新生児肺炎」を発症すると言われています。
*新生児結膜炎:まぶたの腫れ、多量の膿を含んだ目やになどの症状が生後5~14日目に発症します。
*新生児肺炎:多呼吸、喘鳴(ぜんめい ゼイゼイ、ヒューヒューという呼吸音)、 痰や喀血(かっけつ 口から血を出すこと)を伴う咳などの呼吸器症状が見られます。
クラミジアの治療
妊婦さんがクラミジアに感染すると、上記のような流産や早産、産道感染のリスクがあるため、妊娠30週までにはクラミジア検査を行います。
妊娠中にクラミジアに感染した場合でも、医師の指示のもと治療を受ければ、安心して出産に臨むことができます。
私の病院では、母子手帳を受領してすぐの10週~12週くらいでクラミジア検査を行いました。
妊娠中の場合、お腹の赤ちゃんに影響を与えない抗菌薬(アジスロマイシンやクラリスロマイシンなど)を使用します。抗菌薬の種類にもよりますが、1~7日間程度服薬して、それから2~3週間後に再検査を受けてクラミジアがいなくなっていれば治療終了です。
治療期間は1か月程度です。
また、再感染を防ぐためには、「夫」にも検査を受けてもらうことが必要になります。
BV(Bacterial vaginosis)
細菌性腟症(Bacterial vaginosis:BV)は、常在菌にかわって異常細菌が増殖した状態のことをいいます。
妊娠中の影響について
細菌性腟症だけでは腟炎と違って症状にあらわれることがありませんが、異常細菌が頸管に沿って感染していき、赤ちゃんや羊水を包む卵膜にまで達すると「絨毛膜羊膜炎」と呼ばれ様々な病態を引き起こします。
また、分娩時に赤ちゃんに産道感染を起こし、肺炎や髄膜炎などを起こすことがあります。
BVの治療
治療は腟内の消毒や抗生物質の投与、「ウリナスタチン」という炎症を抑える作用のある薬剤の投与があります。
炎症が拡がれば、赤ちゃんに影響が及ぶ前に娩出させることもあります。
妊娠中は規則正しい生活習慣を心がけ、免疫力が低下することのないように体を健康に保つことが大切ですね。
GBS(B群連鎖球菌)
GBSは、腟内、外陰部、肛門付近に常在する菌の一つで、妊婦さんの15〜40%でみられると言われています。
常在菌であるため、自覚症状はありませんが、安全な出産のために、妊娠経過中この菌には特に注意が必要です。
妊娠中の影響について
出産のとき、産道を通る際に赤ちゃんに感染して「細菌性髄膜炎」や「敗血症」、「肺炎」など起こすことがあります。
とは言え、GBSを保有している妊婦さんから生まれた赤ちゃんみんなにGBSが伝わってしまう訳ではないそうです。
伝わってしまった場合も、実際に感染症を発症する率は1%以下と言われています。
GBSの検査・治療
妊娠後期(36週前後)におりものの培養検査をすることによって、GBSを保有しているかどうかが分かります。
GBSを保有していると分かった時点から抗生剤を1、2週間内服し治療します。
GBSはビクシリンなどペニシリン系の抗生剤がよく効くので、一旦は検査で陰性になることもありますが、再発する場合も多いので、赤ちゃんへの感染を予防するにはこれだけでは十分ではありません。
赤ちゃんへの感染を防ぐためには、お産のとき、陣痛が始まった時点もしくは破水が分かった時点にペニシリン系の抗生剤を点滴します。
抗生剤により、菌の感染力が最小限になっている時に赤ちゃんが産道を通ってくると、感染する可能性はかなり低くなります。
妊娠中のおりもの検査 まとめ
調べてみると、こういった特定の「菌」を持っていると、赤ちゃんに影響を与える可能性があります。
どの検査がどんな病気の検査で、自分や赤ちゃんにどんな影響があるのか知っていると安心できますね(・∀・)
菌を有することがわかっても、先生の指示に従えば赤ちゃんへの影響を最小限に抑えることができます。
そういう意味でも「妊婦健診」をきちんと受診することは、とても大事なことですね。
先生や看護師さん・助産師さんと2人3脚で無事に出産できるように頑張りましょう!
では、また。
-
前の記事

妊娠中「手の関節が痛い」「手の指が曲げにくい」のはなぜ?原因と対策を調べてみた。 2020.04.01
-
次の記事

【口コミ】ベビーバスは「折りたたみ式」が断然おすすめ!カリブのベビーバスを実際に使ってみての感想。 2020.04.06








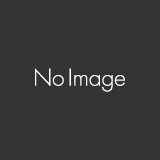




コメントを書く